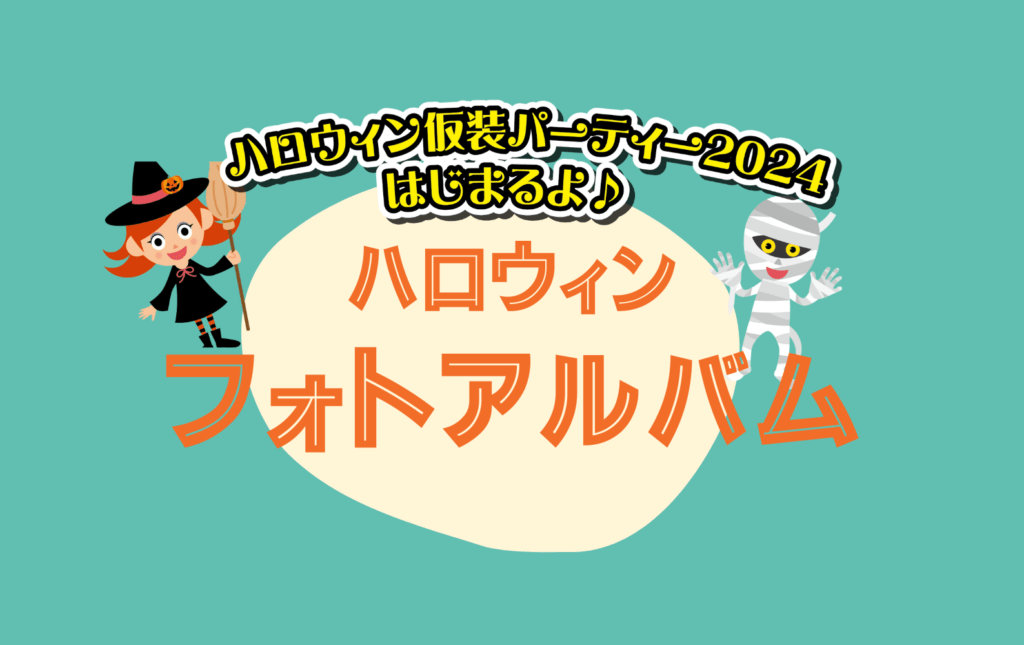市川・浦安・江戸川区ベイエリアで、動き出す人を応援するコーナー「ジモトを動かす人」。
第1回目は、「浦安三番瀬を大切にする会」で活動されている樋山裕己さんをご紹介します。
浦安三番瀬を江戸前の豊かな海に! プラごみを減らし、海草を増やす!
樋山裕己さん
市民が主体となり、地域行政と一緒に浦安の海の環境保全に取り組んでいる「浦安三番瀬を大切にする会」(今井学代表)の樋山裕己さん(浦安市在住)にお話をうかがいました。

東京湾のゆりかご「三番瀬」とは
三番瀬は、稚魚や貝が育ちやすい環境で「東京湾のゆりかご」とも呼ばれます。中でも浦安市の三番瀬は、内湾で唯一の天然干潟が残る貴重な場所です。

プラスチックごみ削減への取り組み
「いま力を入れているのは、浦安三番瀬からプラスチックごみを減らすことと、海草を増やすことです」
マイクロプラスチックと呼ばれる5ミリ以下のプラスチック破片のごみは、海の生物の体内に取り込まれ障害を引き起こします。そこで「プラごみ一層作戦」と題するリーフレットを作成。毎月第一日曜日に行なっている海岸のごみ拾い活動では、マイクロプラスチックも収集しています。
さらに、色とりどりのマイクロプラスチックを材料として、絵やアクセサリーなどを作るワークショップを開催し、親子などで楽しみながら海洋プラスチック問題について考える場を設けています。



海草を増やし、藻場を再生する活動
「三番瀬は渡り鳥の越冬地でもありますが、近年その数が減っています。それは藻場が減り、鳥のエサとなる魚貝が減ったからです。そこで、海草を植え、藻場を造成する取り組みを始めました」
海水温の上昇、海洋汚染などで藻場が減ると、海産物の減少につながり、漁業や日々の食生活にも影響します。
藻場は面積当たりのCO2吸収量が、地上の森の1.3倍と言われます。森林などのCO2吸収をグリーンカーボンと呼びますが、海草の森についてはブルーカーボンと呼ばれ、温暖化対策のメカニズムとしても注目されています。


1999年から続く市民主体の海岸保全活動
「会は1999年に海岸のごみ拾いから始まり、ずっと続いてきました。私は東日本大震災から本格的に参加しましたが、歩みを受け継ぎ発展させていきたい。」

会のウェブページでは、このほかにも観察会やさまざまなワークショップのお知らせを発信しています。
「浦安三番瀬を大切にする会」
webサイト
気軽に参加できる海の保全活動へ
「肩の力を抜いて出来ることからでいいですよ。ちょっと海が見たくなったら、参加してみてください。」